近年、オルガノイドと呼ばれる臓器モデルを作る研究が盛んに行われています。オルガノイドは、幹細胞やiPS細胞を目的の臓器の細胞に分化させ、さらに立体的に培養することで、細胞同士の相互作用や臓器の働きを一部再現するものです。脳を模したオルガノイドも作られており、脳科学研究の新たなアプローチとして注目されています。東京大学 生産技術研究所の池内 与志穂 教授は、脳オルガノイドに工夫を凝らし、他の研究者らがあまり試みていないユニークな方法で、複雑なヒトの脳の働きの秘密に迫っています。
つながりが複雑な脳の働きを生む

提供:池内 与志穂 研究室
これは何の写真に見えるでしょうか。発芽したばかりの植物の種子のようでもあるし、何かの菌のようでもあります。実は、これは、ヒトのiPS細胞を培養して作られた2つの「脳オルガノイド」を、「軸索」と呼ばれる神経細胞の突起でつなげた、「コネクトイド」と呼ばれる物体です。どこかほのぼのした印象を与える見た目ですが、これこそが池内教授の研究のユニークさを示しています。
脳オルガノイドは単なる神経細胞の集合体ではなく、その一部では本物の脳と同じように神経細胞同士が電気的に信号をやり取りする様子まで観察できるのが特徴です。ただし、実際の脳は、大脳皮質や海馬、小脳といった異なる部位が軸索を介して接続し、情報をやりとりすることで複雑な機能を発揮しています。これまでの脳オルガノイド研究の多くは、特定の部位を模して作られたものにすぎず、その内部での活動は観察できても、部位を越えた相互作用までは再現できませんでした。この限界を突破しようとしているのが、池内教授らが作り出したコネクトイドです。
「私たちの研究室では、神経細胞が軸索を伸ばす方向を空間的に制御する手法を開発しました。もともとは運動神経組織の研究が出発点でしたが、それを大脳皮質の神経細胞にも応用できるのではないかと考えました。専用のデバイスに2つの大脳皮質オルガノイドを配置し、軸索の方向を制御してもう一方へと伸ばすことで、オルガノイド同士をつなぐことに成功しました。これは、右脳と左脳が脳梁で結ばれている私たちの脳に似ています」

提供:池内 与志穂 研究室
コネクトイドは、単独の脳オルガノイドや、複数のオルガノイドを融合させた「アッセンブロイド」と比べて、より複雑で強い同期的な神経活動を示しました。さらに、軸索の束を刺激すると、その後もしばらく神経活動が強まったままになる現象も観察されました。これは短期的な記憶のモデルともいえる可塑性(履歴に応じて活動を変化させる性質)の反応であり、コネクトイドがよりヒトの脳に近い働きを持つ可能性を示唆しています。
これらの結果は池内教授自身にとっても、大きな驚きでした。
「脳オルガノイドが軸索を介してつながることで、その活動がよりヒトの脳に近づいたことは非常に興味深いですね。ヒトの脳が右脳と左脳に分かれて軸索でつながっているのはなぜなのか、昔から不思議に思っていましたが、やはり神経細胞の塊同士が一定の距離を保ちながらつながることが、脳の機能を発揮するうえで重要なのだと思いました。脳の中を情報が駆け巡り、複雑な経路を通ることが、複雑な脳の働きの基盤になっているのではないでしょうか」
池内教授は「今後はさらに異なる脳部位のオルガノイドをつないで実験を進めていきたい」と語ります。さまざまなコネクトイドを作成することで、脳全体をシステムとして理解するための重要な手掛かりが得られると考えています。
工学的アプローチで生命科学の研究をする
池内教授が専用デバイスを使ってコネクトイドを作る研究を始めたのは、当時東大生研の藤井 輝夫 教授のもと「マイクロ流体デバイス(非常に小さな溝やトンネルで液体の流れや細胞の挙動などを制御できるもの)」の研究をしていた川田 治良 研究員との共同研究がきっかけでした。
「脳オルガノイド同士をつなぐためには、三次元で軸索を制御する必要がありましたが、従来の二次元の培養技術をそのまま応用しようとしてもうまくいきませんでした。そこで、別の方法を試すことにしたのです。よりシンプルなデバイスを作り、軸索が自ら伸びたくなるように誘導する溝の幅や深さや培養条件などを工夫することで、軸索でつながった脳オルガノイドを作成することができました」
池内教授は簡単そうに話しますが、コネクトイドを作る技術は他の研究グループが容易に真似できるものではありません。長年にわたり軸索の培養を行ってきた池内教授は、軸索の性質を熟知していました。そこに川田研究員が持ち込んだ工学的なアプローチを掛け合わせることで、他の研究者とは異なる独自のポジションが築かれたのです。
「私はずっと、エンジニアリングがやりたかったのかもしれません」と池内教授はこれまでの歩みを振り返ります。
「私は2007年から2014年までアメリカで神経の形態形成や発生におけるタンパク質の役割などを研究していました。日本では2008年に笹井 芳樹 先生が、ES細胞から現在の脳オルガノイドの先駆けとなる神経細胞の立体組織の作製に成功されました。そのニュースをアメリカで聞きながら、バイオロジーのあり方がどんどん変わっていく感じがして、とても面白いなと思っていました」
2014年に帰国して生研に研究室を構え、研究者としてどのように身を立てていくかを考えていた池内教授は、川田研究員との出会いをきっかけに新たな可能性を見出しました。ヒトの細胞を使った脳オルガノイドの研究に工学的手法を掛け合わせることで生まれたコネクトイドは、実際の脳では決して観察できない現象を捉えることを可能にし、脳研究の未踏の領域に踏み込む道が開かれたのです。
医療とコンピュータ技術を変える脳科学の未来
コネクトイドの研究は、どこへ向かっていくのでしょうか。未来を見据える池内教授の視線は、実にさまざまな方向へ向けられていました。
「この研究の未来についてはいろいろ考えられますが、まずは医療の応用につながってほしいと考えています。高度な脳の働きに関わる病気は細胞実験では薬の効果を判定しづらく、動物を用いた研究でもわからないことが多くあります。ヒトの脳の働きを模したコネクトイドができれば、新たに開発した薬の効果をより正確に検証することができます。また、患者さんの細胞を使ってコネクトイドを作成して研究できれば、病気のメカニズムを解明できるかもしれません」
さらに池内教授は、オルガノイドやコネクトイドのような人工脳組織を用いて脳機能の原理を探り、その成果を生命の進化や、高機能なコンピュータ開発へと生かすことも視野に入れています。実際に、脳オルガノイドに計算させ、コンピュータとして活用する技術も進めているそうです。

脳オルガノイドを使ったコンピューターのチップ
提供:池内 与志穂 研究室(撮影:ドゥンキー智也 特任研究員)
そのような未来に向かっていくために、現状で乗り越えるべき課題は何でしょうか。池内教授からは、意外な答えが返ってきました。
「今の課題は、私たちが細胞の『飼育員』をしていることですね。現在、最も労力がかかるのは細胞を育てる工程なのです。オルガノイドにはどうしてもばらつきが出ますし、細胞を安定して育てる条件もまだ試行錯誤の最中だからです。もちろん、細胞を育てる地道な作業の中にも研究の楽しさはあります。しかし、もっと大きく研究を発展させるためには、研究者がいつまでも飼育員であってはいけないのです。細胞の育成はロボットに任せて、研究者は論文を書いたり新しいアイデアを練ったりと、本来の創造的な作業に力を注げるようになるといいですよね」
工学との掛け合わせでコネクトイドが生まれたように、これからの生物学は全く違う分野を掛け合わせることが必須になっていきます。複雑な脳の機能を解明していくためにも、さまざまな分野の研究者の力が必要だと池内教授は語ります。
「実は、ひそかに、この研究所の名前をいつか『脳生産技術研究所』に変えたいという野望を抱いています(笑)。脳を作るには、AI、電気工学、素材科学、化学、医学など、そういった人たちとたくさん関わることが大事ですし、研究者同士のコミュニティをしっかり作ることも、とても重要だと思っています。生研には100を越えるさまざまな分野の研究室がありますから、みんなの力を合わせて脳を作ったら、きっと面白いことができるんじゃないでしょうか」
軸索を伸ばしてつながる脳オルガノイドのように、池内教授の研究も軸索をのばし、どこかでつながり、新しい世界を見せてくれるのでしょう。謎に包まれた脳の新たな一面が明らかになる日が待ち遠しいです。
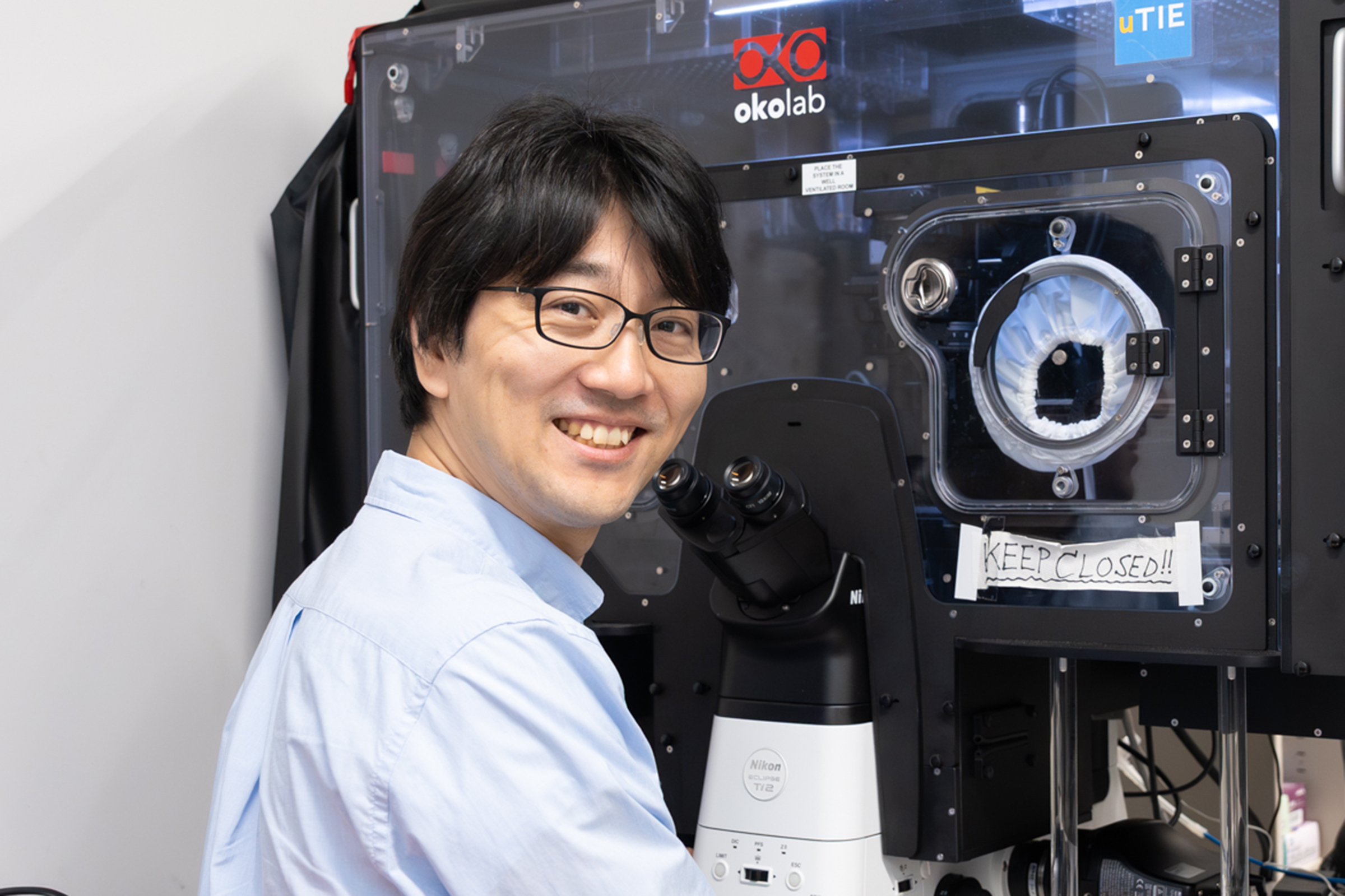
“Complex activity and short-term plasticity of human cerebral organoids reciprocally connected with axons “, is published inNature Communicationsvolume 15, Article number: 2945 (2024) at DOI: 10.1038/s41467-024-46787-7
関連記事≫ 体の外に作った神経回路が、外部メモリーに?

【紹介研究者】
池内 与志穂(東京大学 生産技術研究所 教授)
専門分野:分子細胞工学
記事執筆:寒竹 泉美(サイエンスライター・小説家)


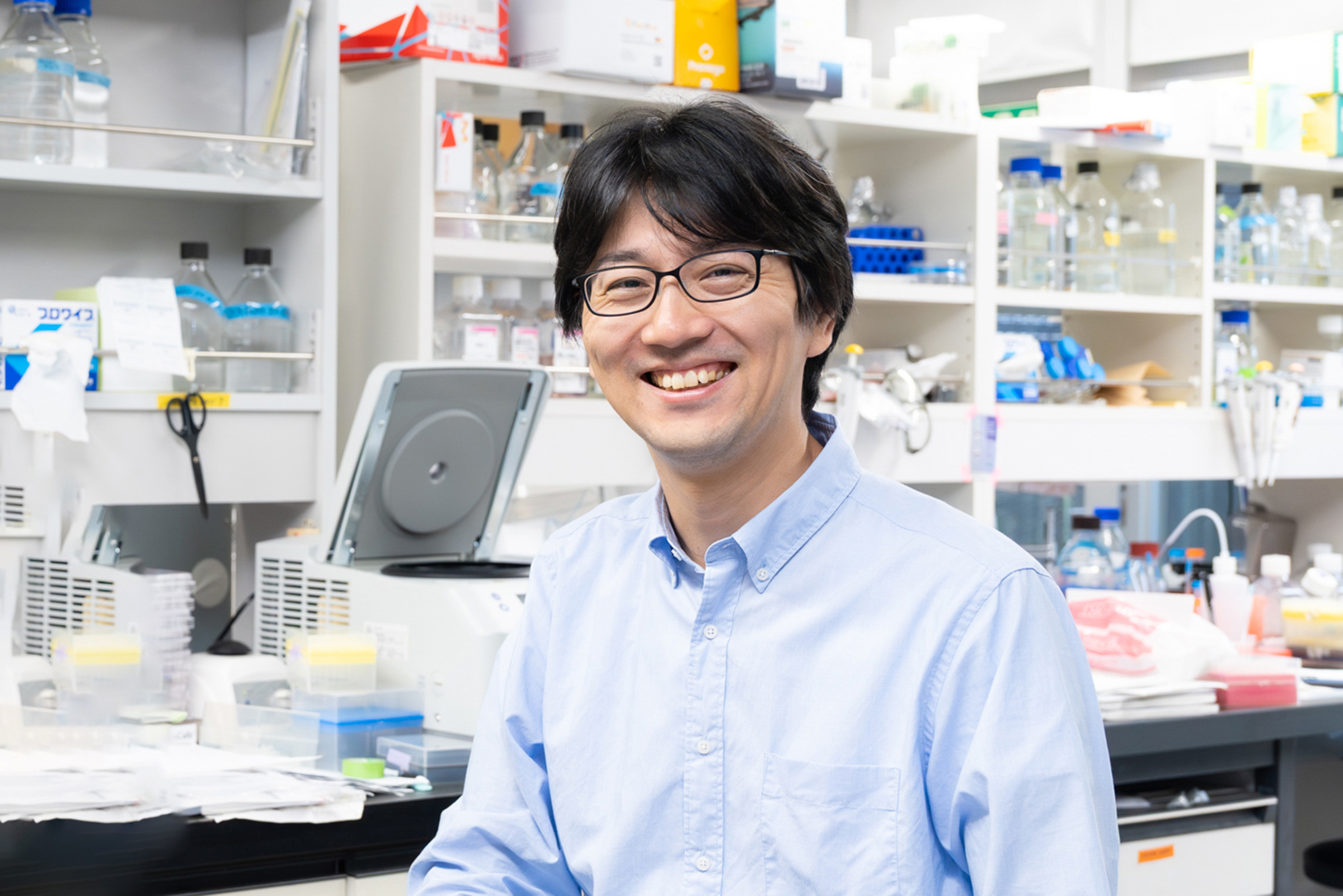
みんなのコメント
コメントはまだありません。
投票&コメントで参加
この記事が描く「もしかする未来」をどのように感じましたか?あなたの期待度を投票してください!
もっと詳しい研究内容を知りたい方、疑問や質問がある方は、研究室のウェブサイトをご覧ください。
この記事をシェア